受験生の方へ
在校生の方へ
保護者の方へ
企業の方へ
一般の方へ
卒業生の方へ
お問合せ
令和7年3月 発行
校長 鶴見 智

「井の中の蛙」という言葉がある。皆さんもよく知っていると思う。中国の古典「荘子」にあるものだが正確には「井の中の蛙、大海を知らず」である。他の広い世界のあることを知らずに自分のまわりのせまい範囲だけでものを考えていることのたとえである。その言葉を頭に置きながらあらためて本校の校是について考えてみたい。
学校だより「志遠」の名は本校の校是「身近而志遠」(中国・魯の歴史書「春秋左氏伝」)からとったものである。意味は「偉大な志をもって雄飛する」と由来にある。学生にはここ北九州高専のキャンパス雄志台から飛び立ち飛躍してほしいという思いが込められている。
今、私からあらためて皆さんに校是「身近而志遠」を送りたい。井の中の蛙から脱し、世界を見てほしい。本物に触れてほしい。なお、私が「志遠」に寄稿するのはこれが最後になるかと思う。皆さんがこの稿を読んでいるときには他高専に着任している。私も北九州高専の校是を胸に抱いて飛び立つつもりである。
教務主事 前田 良輔
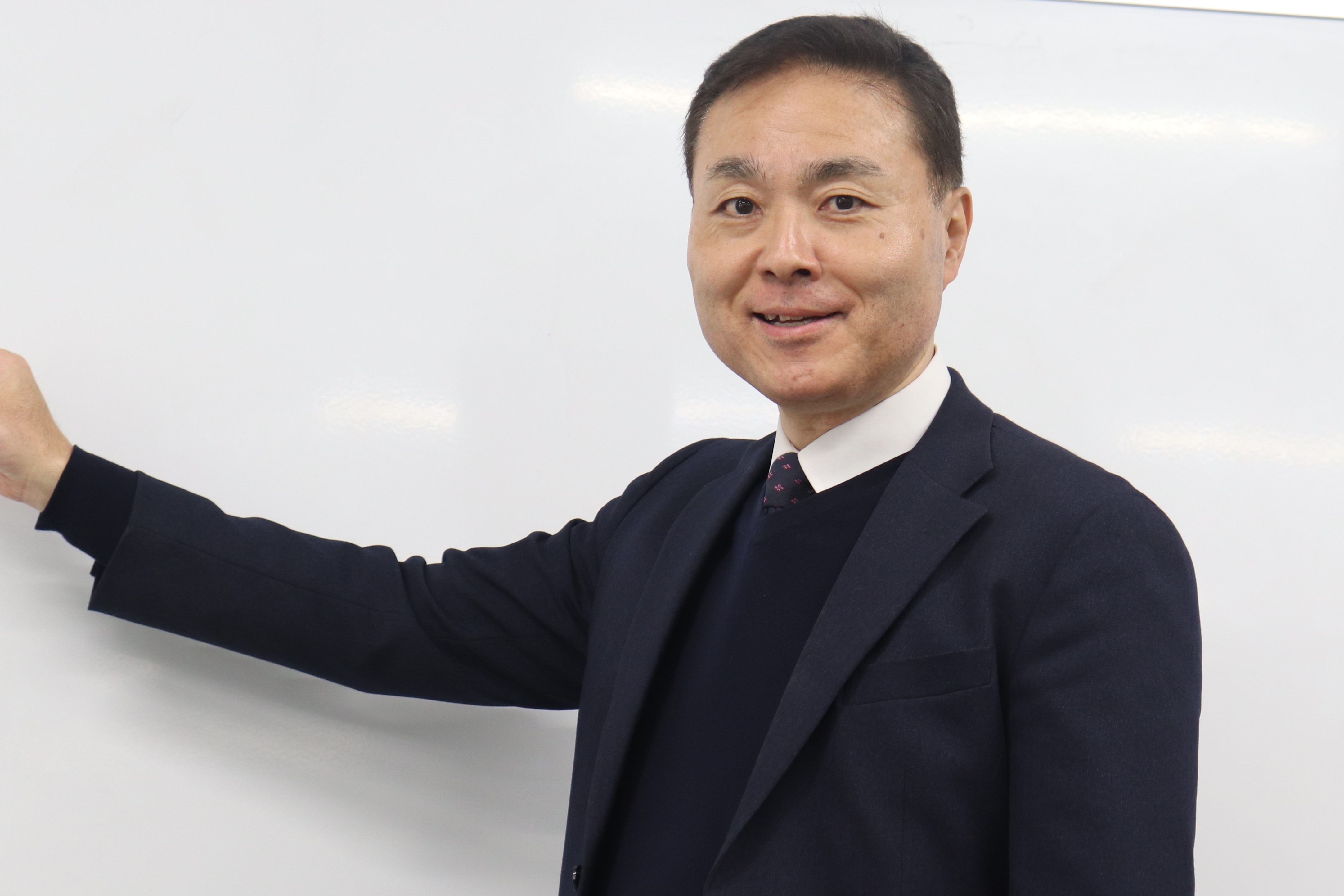
物事の視点を表した言葉です。虫の眼とは、虫のように地を這いながら目の前で起こっている出来事を観察し、分析するといった視点です。鳥の眼とは、地上で起こっている細かな事象の積み重ねとして、大空から地圏や水圏の様子を観察する視点です。最後に、魚の眼とは、目玉で見えるものと言うよりは肌で感じる潮目や趨勢のような感覚的あるいは直感的な視点と言えるでしょう。
2年生科目「材料基礎」の観点で検証すると、材料は私たちの役に立つようにと虫の眼をもった人々によって研究・開発され究極の適材適所で私たちの身の回りに存在しています。また、鳥の眼によって材料を資源や廃棄物の視点からみると、資源の枯渇や海洋プラスチック問題といった陰の部分も見出すことができます。最後に魚の眼です。この先、社会からどんな材料が求められるでしょうか。この答えを導くためには、本校での学びだけでは難しいでしょう。感度の良いアンテナを張り巡らし、様々な異分野の集団に身を置きながら専門性を活かす必要があるかもしれません。その中でピン!とくるものだと思います。そんな視点を身につけてほしいと思いながら授業をしています
5年機械創造システムコース 長明 佳里奈

北九州高専での5年間の学校生活、沢山の人々に支えて頂き、様々な仲間との思い出を創ることができました。
高専の授業では実験や実習でみんなと助け合う場面が多く、クラスの絆がとても強かったと思います。特に4年生から5年生で行った創造デザイン演習では、チーム内だけでなくクラス全体で協力し合い先生方からも助言を得ながら、それぞれ個性豊かなロボットを完成させました。走行テストでロボットを動かした時のみんなからの歓声はすごく、最高の思い出となっています。
高専生として5年間、機械創造システムコースとして3年間、全力で行事を楽しみ苦難も一緒に乗り越えてきた友人達と離れることは想像していた以上に寂しいです。在校生の皆さんには「限られた時間を大切に、チャンスは逃さずに」ということを伝えたいです。時間は残酷なほどに早く過ぎ、何事にも期限があります。いつまでも高専生で、今の環境ではないということをしっかり頭に入れて、後悔の無いよう、学校生活を全力で楽しんでください!
5年知能ロボットシステムコース 古賀 翔也

5年間を終え、高専から釈放されようとしています。
「やっと」と言うべきか、「もう」と言うべきか迷うところですが、振り返ってみると本当に充実した日々でした。
皆さんは、どんな学生生活を思い描いて高専に入学しましたか?私は、毎日が工業に彩られ、卒業する頃にはガンダムやニチアサの巨大ロボのようなものが作れるようになっているのでは…と想像していました。
実際、そこまでの域には達しませんでしたが、授業を通して理論を学び、実習を通して技術と経験を積むことで、少しだけロボットやものづくりについて理解が深まったように感じています。
また、部活動や寮生活では、年齢の異なる仲間たちとともに過ごし、高校や大学では味わえないような青春の日々を楽しむことができました。
こうして充実した時間を過ごせたのは、素晴らしい仲間や先生方に恵まれたおかげです。本当にありがとうございました。
そして、あっという間に過ぎてしまう高専生活。後輩たちよ、今この瞬間を大切に、思いきり楽しんでください!
5年電気電子コース 江藤 大輝

入学時、この学校には友人はもちろん、顔見知りすら一人もいませんでした。しかし、入寮・入学後すぐに、個性的で温かい友人たちに恵まれました。
寮生の友人たちとは日常生活を共にしながらも、飽きることなく毎日楽しく過ごしました。また、寮生以外の友人にも恵まれたおかげで放課後や休日にたくさん遊び、新しい趣味もいくつか見つけました。楽しいことばかりではなく、特に電気電子コースに所属してからは、試験期間中にプレッシャーを感じることも多々ありました。それでも、先生方や友人たちの支えがあったおかげで、安心して卒業を迎えることができます。
私は、多くの方々に支えられながら、寮長やコース代表といった役割を果たすことができました。これらの経験は、社会人になってからも必ず自信につながると確信しています。
後輩に伝えたいことは、積極的に何かの役割を担うことが貴重な経験につながるということです。その第一歩として、学級幹事に挑戦してみるのがおすすめです。私も5年間続けました。
最後に、これまで関わってくださったすべての方々へ、心より感謝を申し上げます。
5年情報システムコース 花田 瑛斗

高専での生活を振り返ってみると、なんだかんだ長いようで短い5年間でした。よくわからない公式、実験レポート、赤点のラインが60点、などなど、はじめの頃は慣れないことだらけで、とても大変だったことを覚えています。
しかし、高専での日々は他の高校、大学では体験することのできないものばかりで、ユニークな生徒や先生による授業、高専ならではの学校行事、高専のみの部活動の大会など、思い返すととても充実した日々でした。
高専では基本的に自由で,行事も生徒が主体になって行うため、行動力が大事になってきます。学級幹事や行事の役職など、迷った時は「とりあえずやってみるか」の精神で最初の一歩を踏み出して欲しいです。一歩踏み出してみると案外楽しかったりします。
いろんな友達や部活動の先輩、後輩、そして先生方に支えてもらったことで楽しく、実りのある充実した高専生活を送ることができました。本当にありがとうございました。
皆さんも一度きりの高専生活を楽しんでください!
5年物質化学コース 宮本 奏汰

皆さんこんにちは、5年物質化学コースの宮本です。
北九州高専での5年間を振り返ると、長いようであっという間でした。コロナ禍の遠隔授業に始まり、多くの制限のなか学校生活を送り、制限が緩和されて高専祭や体育祭を満喫できたかと思えば卒業です。もう少し学生でいたかった気持ちと、試験や研究から解放されて嬉しい気持ちが入り混じっています。
私はこの5年間で数えきれないほど多くの経験をすることができました。特に印象に残っているのは、学生会員として高専祭や体育祭の運営に関わったことです。仲間と共に企画や運営に取り組み、その先に生まれた感情や絆は、学生会に入っていなければ経験できないものだと感じています。楽しいことも多かった反面、苦しいことに直面する時もありましたが、今となってはそれもいい思い出です。皆様ぜひこの機会に学生会に入会してみてはどうでしょうか♡
機械創造システムコース 島本 憲夫

卒業後は、それぞれの進路で新たな環境に身を置くことになります。高専でのある意味心地よい環境とは異なり、厳しいと思うことがあるかもしれません。
これからはチームで仕事をする機会が多くなり、メンバの協力は必要不可欠です。皆さんには、まわりの人に信頼される人になってもらいたいと思います。そうすると、「○○さんのためなら協力します」と応援が得られ、「○○さんになら任せて大丈夫」と新たな仕事のチャンスが得られます。無理して自分の身の丈に合わない仕事の仕方をすると疲れてしまいますから、頑張り過ぎずでも謙虚に、まずはあなたに与えられた役割をしっかり果たしてください。でも、これはなかなか難しいことで、全てがうまくいくとは限りません。うまくいかなくても、物事に真摯に取り組んでいる姿勢は、まわりの人は必ず評価してくれるはずです。それが信頼につながる第一歩だと思います。自分はうまくやっていけるのだろうか、と心配に思うかもしれませんが、高専で学んだ皆さんなら出来るはずです。今後の活躍を期待しています。
知能ロボットシステムコース 蒋 欣

卒業おめでとうございます!
初めて担任を務め、3年間、皆さんとともに一から学び、失敗しながら成長し、計り知れない喜びと満足を感じました。一緒に楽しく話したこと、一緒につらい思いをしたこと、一緒に高専祭の準備を頑張ったこと、一緒にクラスマッチで精一杯応援したこと――そのすべての思い出は、私にとってかけがえのない宝物です。これからも心の中で大切にしていきます。皆さんの成長の道のりを共に歩めたことは、本当に幸せでした。
これからは、皆さんのそばで見守ることはできませんが、次の言葉を贈ります。まず、これからの世界では、知識はどこでも学べます。しかし、最も大切なのは、識別力と思考力を身につけることです。次に、世の中は目まぐるしく変化しますが、最初の志と粘り強さを貫くことが、成功の鍵となります。そして最後に、心を広く持ってください。周りの人を愛し、許し、支え合うことで、他人に振り回されることなく、自分の人生を主体的に歩むことができます。
皆さん、人生という試練に向き合う準備はできていますか?学び舎を離れても、社会に出ても、常に挑戦する心を持ち、粘り強く誠実な人格を貫き、逆境に負けずに自分の道を歩んでいけるよう心から願っています。
電気電子コース 小畑 大地

転職してきたと同時に担任かぁ・・・後悔してももう遅い。しょうもない小説のような感想から始まった、担任としての生活。
最初は少し大人しい子が多いなと感じましたが、体育祭やクラスマッチ等の行事を通じて、徐々に打ち解けられたと思います。仕事と称して高専祭後にボーリング行ったり、宿直と称してキャンプ行ったり、妻の居ぬ間に自宅で卒研打ち上げやったり、今となってはいい思い出です。
さて、皆さんはこれから、大学や社会で揉まれて苦労することもあるでしょう。しかし、少なくとも電気分野の能力に関しては、前川先生の回路・私の電磁気・本郷先生の演習を乗り越えてきた皆さんに、恐るべきものはありません。自信を持って、輝かしい未来を掴んでください。
いつかまた遊びに来て、お酒でも飲みながら近況を話してくれるのを楽しみにしています。妻には内緒でね。
情報システムコース 北園 優希

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
2年間の担任でしたが、皆さんと過ごした日々は、私にとっても忘れられない思い出ばかりです。特に、体育祭の応援の部での連覇、高専祭での2年連続の校長賞受賞、情報システムコースとしては珍しいクラスマッチでの入賞など、数々の輝かしい成果を見せてくれたことはとても印象に残っています。これらの行事に向かって取り組むチームワークと一生懸命な姿勢は、学校全体に良い影響を与え、我々教員も心から誇りに思っています。
これからそれぞれの道を歩むことになりますが、北九州高専で培った知識や経験は必ず皆さんを支える大きな力になるでしょう。どんな環境でも、これまでの経験を活かして、自分らしく進んでいってください。
皆さんの未来が明るく、素晴らしいものであることを心から願っています。これからも自分らしく輝き続けてください。いつまでも応援しています。
物質化学コース 後藤 宗治

ご卒業おめでとうございます。
長い高専生活も3月で終了ですが、これで終わりではありません。4月から新しい環境での生活が始まります。そこで皆さんへのアドバイスですが、教科書類は学校に置いて行かず(捨てずに)持って行ってください。進学する学生は進学先で復習することもあります。就職する学生も仕事で必要になる場合が多々あります。実際、私は学会の依頼で幾つかの企業へ化学工学の授業の講師として派遣されることがあります。企業では学校で学んだ知識を基に各企業のノウハウを用いて、生産活動を行っているので、その基礎を学び直しのためにその講習会に参加する方の割合が一番多いです。第二の理由は全く新しい分野の仕事をすることになったのでその分野の基礎が必要になったでした。
進学するにしても就職するにしても、本校で学んだ知識が必になることも多いと思いますので教科書や授業ノートは大切にしてください。
学生会長 山岡 松平

皆さんお疲れ様です。初めましての方は初めまして、学生会長の山岡です。
この文章を書いている1週間後にはなんと卒業式があるみたいです。あっという間ですね。
学生会役員になってからの2年間は楽しいことだけではなく、仕事や人間関係に悩まされ、あまりのストレスで胃に穴をぶちあけたり、不眠症や躁うつ病を患ったりと、自分の弱さを痛感させられる日々でした。現実はアニメのヒーローのようにはいかないみたいです。
そんな弱弱の実の全身貧弱人間の僕がこうして最後まで学生会長として走り切れたのは、手を差し伸べて背中を押してくれる大切な人達がいてくれたからです。
苦しくて逃げ出した時に探し出してくれる人、自分を信じて最後までついてきてくれる人、一緒にくだらないことで大笑いしてくれる人、みんなが自分に手を差し伸べてくれた最高のヒーローです。感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。
それでは最高のヒーローのみなさん、またどこかで。サラダバー。
電気電子コース 小路 紘史

【私の生活にAIが浸透し、学び方も大きく変わりました。インターネット検索やAIによる要約機能を使えば、一瞬で思わな情報にアクセスできます。たとえば、AIが生成した文章に対して「本当に正しいのか?」「他の視点はどうか?」と問い直す習慣を持つだけでも、大きな差が生まれます。技術の進化は私たちを助けてくれますが、最後に価値を高めるのは自分自身の思考力です。AIと共存しながら学ぶ力を磨いていきましょう。】
これは生成AI(GPT4.0)を使って生成した文章です。注意喚起をしつつも、利用を促し、生成AIが書いたということを明かせば少し深い感じがします。また、完璧ではなく人間が修正することを前提にしているようにも思えます。
今後は、AI・量子力学・完全食などを「便利になった」ではなく「当たり前」と考えるようになっていくでしょう。AIによる代替が進む時代であっても、世の中の仕組み、人々の営み、物理現象といった普遍的や連続的なものも多くあると思います。高専では専攻を選択して勉強していきますが、その過程では専門性だけでなく、自身の能力を磨き、見識を広げ、技術や道具を上手く使えるようになっていって欲しいと思います。
3月7日(金)、同窓会から本校学生の功労賞の表彰がありました。
授与式の様子並びに表彰の内容は、本校同窓会HPからご確認いただけます。